この記事には、広告を含む場合があります。
記事内で提携企業様のサービスを紹介することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
薬剤師が飽和すると言われるようになり、数年が経ちました。
確かに都市部での薬剤師数は充足しており、以前に比べれば確実に薬剤師数は増えてきています。
ただし、実際に薬剤師が余っていると感じる場面は多くはありません。地方ではいまだに薬剤師は不足しているのが現状です。
将来を見据えた場合、本当に薬剤師は飽和してしまうのでしょうか。
今回は薬剤師の将来性と、そのキャリアプランについてもお話しします。
 あや
あや
 モンブラン
モンブラン
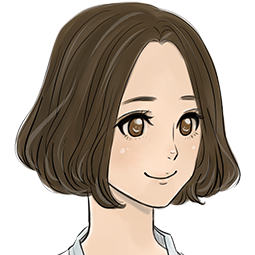 きよみ
きよみ
 モンブラン
モンブラン
| キャリアアップ目的の転職なら!転職サイトランキング | ||
|---|---|---|
マイナビ薬剤師 | じっくり重視 サポートが充実 ミスマッチが少ない | |
薬キャリエージェント | スピード重視 優良な病院求人 細かなニーズにも対応 | |
ファルマスタッフ | 派遣重視 研修制度が充実 社会保証完備 | |
2025年問題!薬剤師の需要は一層高まるのか?それとも過剰飽和?
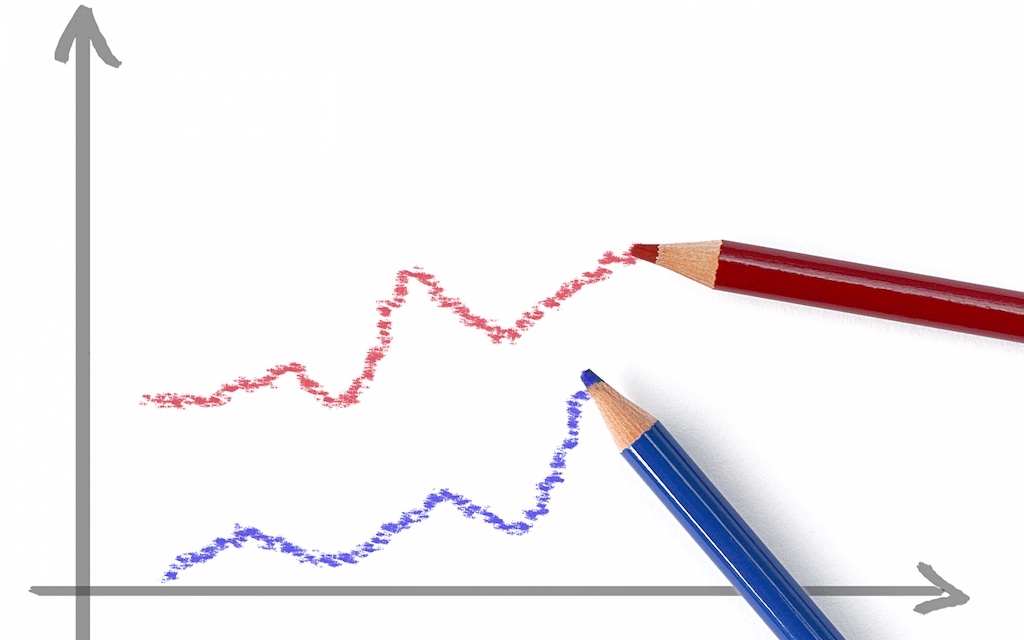
2025年は、団塊世代が75歳以上となり、後期高齢者となる時期です。
これによって後期高齢者の割合は18%を超え、65歳以上の前期高齢者も含めれば、人口の30%を超える超高齢化社会となってしまいます。
この超高齢化社会の訪れを2025年問題と表現しています。
薬剤師免許保持者の需要は飽和状態と言われていますが、それはあくまでも「数値上」です。
確かに薬学部の急増に伴って薬剤師の供給は増加しましたが、高齢者の増加は必要となる医療者の増加につながる為、一概に薬剤師はもう飽和状態にあるとは断言できません。
薬局をめぐる環境の変化
薬局を取り巻く変化の歴史
- 分業推進の終焉:分業体制から患者選択の分業体制へ
- 処方箋の伸び悩み:分業率60%超えで、新規出店の限界
- 技術料収入の伸び悩み:医療費抑制策
- 利益の縮小:ジェネリック、長期処方箋で利益現業
- 競争激化:ドラッグストアの調剤参入
- 合併・買収・提携:M&Aの活発、異業種間の提携
- アンチ分業:調剤医療費増加への批判
- 薬局の構造規制:門前薬局からかかりつけ薬局へ
- 調剤依存体質の危機:医療機関の下請け調剤の危機
- IT化:薬歴の個人管理、情報一元化
調剤薬局を取り巻く環境は、決して恵まれているとは言えない状況になっています。
医薬分業は頭打ちとなり、それに伴って処方箋枚数も伸びることはありません。
医療費削減の影響によって調剤報酬は毎回マイナス改定され、ジェネリック医薬品が中心の医療となったことで薬価差も少なくなっています。
過去には出店するだけで儲かると言われていた時代もありましたが、現代では閉店や経営統合を余儀なくされる薬局も存在しています。
このままの状況が加速していけば、調剤に依存した経営を行っている薬局は淘汰されていくことになってしまうでしょう。
薬局の店舗数はコンビニよりも多い約5万8000件
薬局の店舗数は、コンビニよりも多くなっています。
出店すれば儲けが出る状態が長く続いた弊害とも言えますが、これだけの数が本当に必要なものなのでしょうか。
薬局のグランドデザイン2014(日本薬剤師会が定める2025年に向けての方針)から見れば、現在の薬局数は適正数を上回っている明らかなオーバーストア状態であることがわかります。
すでに薬局の淘汰も始まっている状況の中、最近ではドラッグストアが調剤に参入するようになり、ドラッグストアも交えた生存競争、そして、薬局の合併や買収が盛んに行われているのです。
分業率70%超え、処方箋枚数の伸びが鈍化
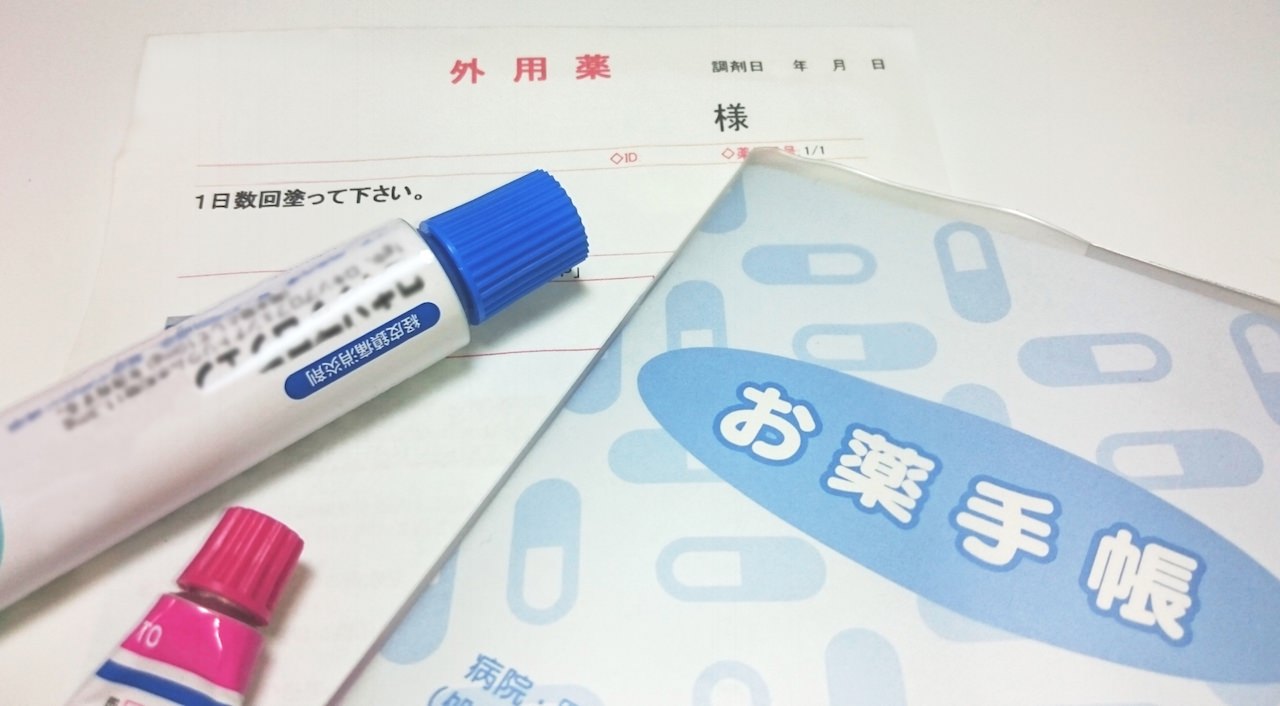
1995年〜2005年の10年間では、医療機関がこぞって院外に処方箋を発行し、それに伴って薬局数も増加していきました。
一つの診療所に最低でも一つの調剤薬局が出店し、大病院の門前では3軒以上の調剤薬局が立ち並ぶ状況となりましたが、現在はその出店ラッシュも鈍化しています。
その理由は、新たに処方箋を発行する機関がなくなり、出店する場所がなくなったためです。
現在の調剤薬局は需要に対して供給過多となっているオーバーストア状態と言われています。
昨今のオーバーストア化している現状では、調剤だけに依存している調剤薬局は淘汰される運命にあるため、調剤だけに依存しない経営の柱をどう構築するかがカギとなるのです。
今後の調剤薬局が生き残るためには、下記のような専門性を発揮できるかどうかがポイントとなります。
調剤薬局が生き残るためのキーワード
- 予防医療
- 漢方やサプリメント
- 無添加商品
- 在宅医療
- オリジナル商品の販売
- ネット対応
治療から予防医療へ!
現代の風潮は、治療から予防医療にシフトしています。
セルフメディケーションが一般に認知され、体調を悪化させないための医療が推進されているのです。
治療が必要となる状態にならないようにしていくため、病院に受診する機会は減り、その結果として処方箋の発行も減少することが予想されます。
そのため、調剤にのみ依存している経営では、調剤薬局として維持していくのは困難になるでしょう。
しかしながら、薬剤師という職業は治療に関わるだけではなく、予防にもその職能を発揮することができます。
サプリメントや食品など、薬学的な観点からのアドバイスを実施できるのは強いアドバンテージとなるのです。
選択される薬局となり、選ばれる薬剤師になるため、専門性を高めておくようにしましょう。
 あや
あや
 モンブラン
モンブラン
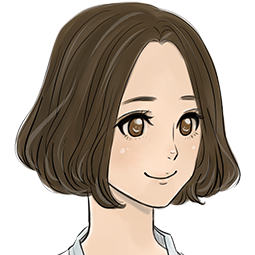 きよみ
きよみ
 あや
あや
 モンブラン
モンブラン
調剤薬局・病院でますます進む機械化・自動化
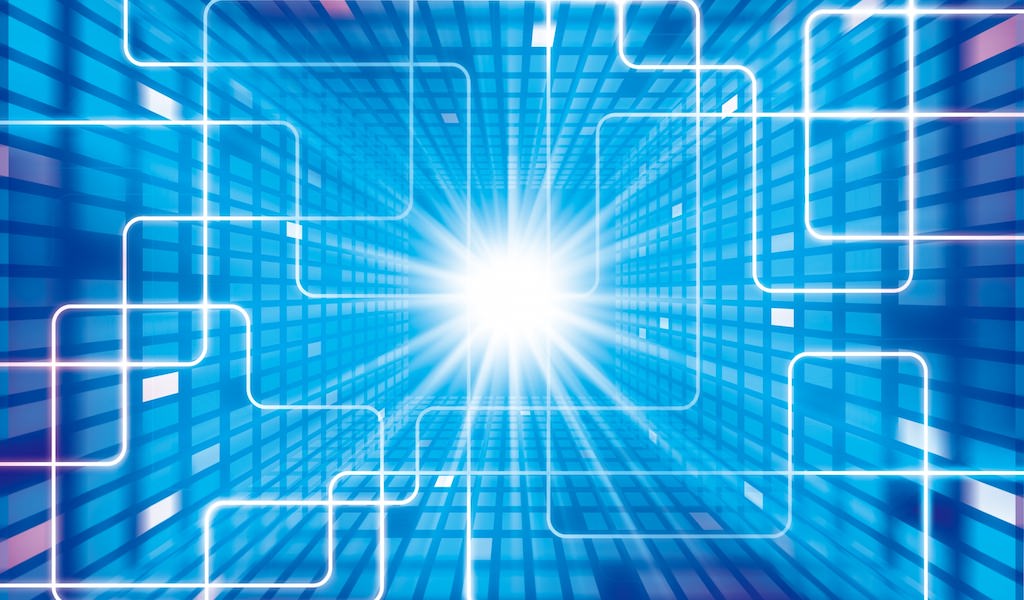
自動分包機を筆頭に、調剤の現場ではどんどん機械化・自動化が進んでいます。
水剤・散剤の自動分包機や電子薬歴など、薬剤師業務のサポートを行う機器が登場したことにより、調剤の現場は大きく変革を遂げました。
たとえば散薬調剤ロボットが販売されたことで下記の様々なメリットが生まれました。
調剤ロボットの導入メリット
- 調剤過誤や医療事故を減らすことができる
- 投薬や疑義照会に専念できる
- 調剤時間が減ったことで在宅医療業務に携わることができる
- 患者を待たせる時間を少なくできる
機械化・自動化を労働者の仕事を奪うモノと考えるのか、業務の「最適化」と考えるのかで自身のキャリアは大きく変わっていくでしょう。
機械ができる仕事は限られていますが、人間が関わらないことによって不要なミスがなくなることは最大のメリットだと言えるでしょう。
さらに、血の通った人間だからこそできる業務に対して、現場の薬剤師が専念して専門性を発揮できる状況が生まれたことは喜ばしいことです。
服薬指導に重きを置かず、調剤作業ばかり行っていた薬剤師は淘汰されてしかるべきものであり、「ただ」働くだけの労働者は現場から消えていくことになるでしょう。
本業に関わる専門性を高めたり、本業以外のスキルを磨いたりした薬剤師が、自動化された薬局の中でも生き残っていくことができる薬剤師となっていきます。
医療保険制度が整う日本とは異なる海外の薬事規制

国民皆保険制度を実施している日本とは異なり、諸外国では保険の加入を任意で決めている場合がほとんどです。
それも含めて、諸外国では自身の収入によって受けられる医療に差が生まれることが、日本との最大の違いだと言えるでしょう。
保険制度が異なることによって、医療を管理している制度にも違いが生まれます。
アメリカ・イギリス・ヨーロッパ諸外国の薬事規制
| 医薬品 | 分類 | 販売形態 | 開設要件 | 取扱者 | |
| アメリカ | 処方医薬品 | 医師の処方による | 薬局 | 管理薬剤師 | 薬剤師、テクニシャン |
| 非処方医薬品 | 小売店で販売可能 | 小売店 | なし | なし | |
| ヨーロッパ | 処方医薬品 | 毒性と安全性・形と容量・利用の目的 | 薬局 | 薬剤師に限る、法人不可 | 薬剤師、調剤助手 |
| 薬局薬剤師販売医薬品 | 毒性と安全性・形と容量・利用の目的 | 薬局 | 薬剤師に限る、法人不可 | 薬剤師 | |
| 薬局販売医薬品 | 毒性と安全性・形と容量・利用の目的 | 薬局 | 薬剤師に限る、法人不可 | 薬剤師、調剤助手、薬局助手 | |
| 自由販売医薬品 | 毒性と安全性・形と容量・利用の目的 | 小売店 | なし | なし | |
| イギリス | 処方医薬品 | 医師の処方による | 薬局 | 個人は薬剤師、法人は各店舗に管理薬剤師1人配置 | 薬剤師、薬剤師技師、調剤助手、薬局助手 |
| 薬局販売医薬品 | 薬剤師の監督下で販売可能 | 薬局 | 個人は薬剤師、法人は各店舗に管理薬剤師1人配置 | 薬剤師、薬剤師技師、調剤助手、薬局助手 | |
| 自由販売医薬品 | 小売店で販売可能 | 小売店 | なし | 薬剤師、薬剤師技師、調剤助手、薬局助手 | |
| 日本 | 処方医薬品 | 医師の処方箋による | 薬局 | なし | 薬剤師 |
| 非処方医薬品 | 小売店で販売可能 | 店舗販売業 | なし | 薬剤師、登録販売者 |
実は、米国やヨーロッパ諸国を含めても、日本ほど公的医療保険制度が整っている国は少ないのです。
いつでもだれでも、思い立ったらすぐに病院に行けるのは、各国探しても日本ぐらいのものでしょう。
海外の場合、薬剤師の社会的地位が高いといわれていますが、それはまず病院に行くのではなく、薬剤師に「相談」する必要があるために社会的需要があることと関係しています。
病院に受診するためには高額な費用を用意する必要があるため、薬剤師に健康相談をすることが習慣づけされているのです。
日本の場合には、まず病院に受診しても負担金は少額で済むため、受診するかどうかを薬剤師に相談するというのは一般的ではありません。
さらに諸外国の場合にはリフィル処方箋が実行されているために、病状変化がなければ薬剤師との対面のみで医薬品を手にすることができます。
薬剤師会の中には、海外と同じように薬剤師の社会的価値をもっと高めるべきとの声がありますが、それは国の薬事事情が大きく関わっているため、公的医療保険制度が整っている日本では難しいことなのです。
とはいえ、医療の質を担保するためには医師・看護師・薬剤師・獣医師の人数が確保されていなければならず、特に最近は医師の負担を減らすための制度が模索されています。
薬剤師の地位を高めることは難しくとも、現在の地位は継続して確保されていくでしょう。
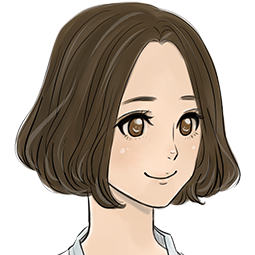 きよみ
きよみ
 あや
あや
 モンブラン
モンブラン
 あや
あや
 モンブラン
モンブラン
求められる薬剤師の共通点は対応力と探求力!将来を見据えたキャリアとは?

今後も薬剤師が飽和するというのは考えづらい状況でありますが、薬剤師数が増加している事実は変えようがありません。
人数が不足している状況であれば、ただ薬剤師免許を持っているだけで昇給・昇進は約束されているようなものでしたが、今後はキャリア構成や能力によって収入や待遇が決まる時代が来ることが予測されます。
ただ働いているだけでは時代の変化に対応できないため、自身の価値は目減りしていきます。
漫然と毎日を過ごしている薬剤師では、今の状態を維持することすらできなくなってしまうでしょう。
危機感を持ち常に準備している薬剤師だけが「現状維持」することができるのです。
ただし、これはあくまでも現状維持です。
今後求められる薬剤師とは、臨機応変な対応力や自身を高めるための探求力を持った薬剤師であり、ただ仕事ができれば良いというものではなくなってしまいます。
求められる薬剤師となるため、下記のキーワードを心にとめておいてください。
21世紀型薬剤師のキーワード
- 専門性×インターネットリテラシー
- セルフメディケーション
- 常に何かを勉強し得ようとしている
- すぐに対応できるように準備をしている
- 本業以外の勉強時間を作っている
まとめ:変化する薬剤師の存在意義!生き残るためのキャリアプラン!
調剤薬局が置かれている状況は、決して楽観視できるものではありません。
医療費は削減され、処方箋枚数の伸びは期待できず、今まで通りの仕事をしているだけでは経営利益は減少していくこととなります。
その煽りは現場で働いている薬剤師にもおよび、薬剤師数の増加も相まって、仕事のできない薬剤師は淘汰されていくことになるでしょう。
現場の自動化も進み、ただ調剤をしているだけの薬剤師はいらない存在になります。
これからの時代に必要とされるのは、機械にはできない臨機応変な対応ができ、自分自身を常に高め続ける薬剤師です。
専門性を高めていくことで、客観的にも必要とされる存在になることができます。
新時代を生き残っていくための対策は、早い方が良いでしょう。今回の記事が、その補助になれれば幸いです。


